「まさか、うちの家が再建築不可だったなんて…」
相続した実家や、長年住んできた家を売ろうとしたとき――
不動産会社から突然、
「この家は再建築不可物件です」
と言われて、頭が真っ白になる方は少なくありません。
- 「再建築不可って、もう売れないってこと…?」
- 「告知義務があるって言われたけど、何をどこまで伝えるの?」
- 「仲介は無理?買取しかない?損しない出口はどれ?」
でも、安心してください。
再建築不可物件でも、売却する方法はあります。
大切なのは、“告知義務で揉めない”ことと、“最適な売り方(仲介/買取/改善)を選ぶ”ことです。
・再建築不可の理由(接道/私道/43条など)
・売却方法3つ(仲介/買取/再建築可にして売る)の比較
・告知義務でトラブルになりやすいポイントと回避策
・売却価格がどう決まるか(相場の考え方)
・役所で確認すべきチェックリスト
・買取業者選びのコツ(損しない比較軸)
再建築不可物件とは?まずは「接道義務」を押さえる
再建築不可物件とは、いま建っている家を壊しても、新しく建て替えができない土地のことです。
原因の多くは、建築基準法の「接道義務」(道路に一定以上接していないと建てられないルール)を満たしていないことです。
この状態だと、老朽化して住めなくなっても建て替えができず、一般の買主から敬遠されやすくなります。
だからこそ、売却では告知義務が重要になります。
再建築不可になる主な原因(よくあるパターン)
- 接道義務を満たしていない
幅4m以上の道路に2m以上接していない(古い住宅密集地で多い) - 前面道路が「建築基準法上の道路」扱いになっていない
見た目は道路でも、法的に“道路”認定されていないケース - 私道で、通行・掘削承諾が取れない
私道の所有者が不明/共有で合意が取れないなど - セットバック未実施
道路幅が狭く、後退(セットバック)しないと建て替えできない - 袋地(無道路地)・路地状敷地
都市部で土地が細分化され、接道条件を満たしにくい
最重要:再建築不可物件の「告知義務」|揉める人の共通点
告知義務とは、売主が物件の欠陥・不利益情報を買主へ正確に伝える義務です。
これを怠ると、売却後に「聞いてない」「話が違う」となり、契約解除や損害賠償に発展する可能性があります。
再建築不可で「必ず」告知すべき情報
- 再建築不可である事実(理由もセットで)
例:接道義務未達、前面道路が法定道路ではない、私道承諾が取れない等 - 私道の権利関係
通行権の有無、掘削承諾、維持管理費、所有者、共有状況など - 建物の不具合(物理的瑕疵)
雨漏り、シロアリ、傾き、腐食、越境など - 近隣トラブル
境界・通行・騒音など、取引判断に影響するもの
ポイントは、口頭だけでなく「物件状況報告書」等の書面で残すこと。
売主の“自衛”になります。
再建築不可でも売れる理由|買う人は「一般層」ではない
「再建築不可=売れない」と思われがちですが、実際は買う人が違うだけです。
再建築不可を買う層は、以下のような“目的買い”が中心です。
- 投資家:賃貸運用・リノベ転売・民泊ではなく長期賃貸
- リフォーム前提の実需:建て替え不要で住めるならOK
- 隣地所有者:土地を広げたい(接道改善の材料)
- 事業者:倉庫・事務所・作業場など用途が合う
つまり、“一般の仲介市場”で不利でも、“別の市場”では動くということです。
ここを理解すると、売却戦略がズレません。
売却方法は3つ|仲介/買取/再建築可にして売る(比較表)
再建築不可の売却は、基本的にこの3択です。
「どれが正解か」は、あなたの状況(急ぎ/価格/手間/トラブル回避)で決まります。
| 売却方法 | 向いている人 | メリット | デメリット | 売却スピード |
|---|---|---|---|---|
| 仲介 | 時間に余裕があり、価格も狙いたい | 条件が合えば高値も | 買い手が限定/長期化/値下げ圧 | 遅い(数ヶ月〜) |
| 買取 | 早く確実に売りたい/トラブル回避したい | 早期現金化/現状渡し可/交渉ストレス少 | 価格は仲介より下がりやすい | 速い(数日〜数週間) |
| 再建築可にして売る | 接道改善が現実的で、費用負担できる | 市場が広がり価格UP期待 | 時間・費用・近隣交渉が重い | 不確実(数ヶ月〜) |
再建築不可の売却価格(相場)の考え方|何で決まる?
再建築不可の価格は、「再建築不可だから安い」で終わりではありません。
実務では、“使い道がどこまであるか”で決まります。
価格を左右する要素(チェック表)
| 要素 | 上がりやすい条件 | 下がりやすい条件 |
|---|---|---|
| 接道・道路種別 | 法定道路に近い/改善余地あり | 完全な袋地/道路認定が厳しい |
| 私道権利(通行・掘削) | 承諾あり・書面あり | 承諾なし/所有者不明/共有で揉める |
| 建物状態 | そのまま住める/賃貸化できる | 雨漏り・傾き・シロアリ等が重い |
| 立地 | 駅近・需要がある | 需要薄・空室リスクが高い |
| 出口(使い道) | 賃貸・リノベ・隣地需要がある | 用途が極端に限定される |
つまり、「仲介で粘る」より「正しい市場に当てる(買取含む)」方が、結果的に手残りが増えるケースもあります。
売る前に役所で確認すべきチェックリスト(これで失敗が減る)
再建築不可は、不動産会社の説明だけで判断すると危険です。
可能なら、自治体の建築指導課などで、最低限このあたりを確認すると安心です。
- 前面道路は建築基準法上の道路か?(道路種別の確認)
- 接道義務(2m以上)を満たすか?
- セットバックの必要があるか?
- 建築基準法第43条但し書きの適用余地(可能性の有無だけでも)
- 私道の通行・掘削承諾の必要性
ここが整理できると、告知内容もブレず、トラブルが減り、査定も正確になります。
「買取」が再建築不可に強い理由|告知義務トラブルを減らす
再建築不可物件において、買取が強い最大の理由は、買主が不動産のプロであり、リスクを織り込んだ上で買うからです。
買取の主なメリット
- 売却が早い:買主探し不要で、現金化が速い
- 現状のまま売れる:リフォーム・解体・残置物対応も相談しやすい
- 告知義務トラブルが起きにくい:評価前提がプロ仕様
- 仲介手数料が不要:手残りが見えやすい
もちろん、仲介より価格が下がる傾向はあります。
ただし、仲介で長期化→値下げ→維持費負担…となるなら、結果的に買取の方が合理的なケースも多いです。
買取業者の選び方|失敗しない「比較軸」
再建築不可の買取は、業者によって条件が大きく変わります。
比較は「価格」だけでなく、取引条件まで見てください。
- 契約不適合責任:免責の可否/範囲
- 測量・境界確定:費用負担はどちらか
- 残置物:処分負担の有無(そのままOKか)
- 私道承諾の整理:業者が動けるか
- 決済スピード:いつ現金化できるか
最適解は「1社だけに聞かない」こと。
同じ物件でも、得意な会社に当たると条件が変わるため、複数査定で比較が安全です。
よくある質問(Q&A)
Q. 再建築不可を再建築可にする方法はありますか?
可能性はありますが、時間・費用・近隣交渉が必要です。代表例は以下です。
- 隣地の一部取得:接道条件を満たす
- セットバック:道路後退で条件を満たす
- 第43条但し書き許可:行政の個別許可を検討
Q. 旗竿地は再建築不可ですか?
旗竿地=再建築不可ではありません。
竿部分が道路に2m以上接し、道路が法定道路なら再建築できるケースもあります。
ただし、私道・幅員不足・道路認定などで再建築不可になる例もあるため、個別確認が必要です。
まとめ:再建築不可の売却は「正しい手順」と「出口戦略」で決まる
再建築不可物件は、放置すると固定資産税・維持費・老朽化リスクが増え、精神的負担も大きくなります。
一方で、ポイントを押さえれば、トラブルなく売却し、早期解決は十分可能です。
- 売却方法は「仲介/買取/再建築可にして売る」の3つ
- 告知義務は「書面で残す」ほど強い
- 価格は“使い道”で決まる(要素分解が重要)
- 役所確認でブレが減り、査定が正確になる
- 買取は比較軸で選ぶ(価格だけ見ない)
「売れない」と諦める前に、まずは“条件の良い出口”を把握することが最短ルートです。
【全国対応】一番有利な条件を無料査定で確認
- 【ワケガイ】
訳あり不動産・共有持分などにも対応
⇒公式サイトはコチラ
カンタン60秒入力 - 【成仏不動産】
リノベ・転売に強みがあり高価買取に期待
⇒公式サイトはコチラ
オンラインカンタン30秒入力 - 【訳あり不動産相談所】
事故物件・相続による不動産査定にも強み
⇒公式サイトはコチラ
無料査定24時間受付中 - 【訳あり物件買取プロ】
東証上場”AlbaLink”が運営
⇒公式サイトはコチラ
簡単30秒入力、メディア紹介多数 - 【ラクウル】
投資家会員10万人を保有し、高価買取に実績あり
⇒公式サイトはコチラ
30秒カンタン無料AI査定が可能 - 【空き家買取くん(by WISH)】
無料で空き家・トラブル物件の相談も
⇒公式サイトはコチラ



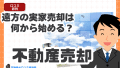
不動産の口コミ評判堂 編集部は、住宅ローン問題・任意売却・競売回避をはじめとした、不動産に関する実務的な情報を発信する専門編集チームです。
元メガバンク融資課出身で、バブル期から不動産金融の現場に携わり、底地ビジネスや立ち退き裁判なども経験した宅地建物取引士の知見をもとに構想・設計を行い、立ち上げました。
現在はその経験を土台に、業者目線ではなく「相談者・当事者の立場で本当に役立つか」を重視し、不動産サービスや専門家を口コミ情報と編集部の実務的な視点を交えて紹介しています。
これまでの情報発信が評価され、フジテレビ系『Mr.サンデー』をはじめ、『健美家』『住宅新報』など複数メディアでの掲載実績があります。